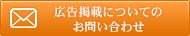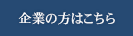- TOP
- ≫ メッセージ
会計実務家コラム
会計ダイバーシティでは、会計領域でご活躍されている実務家の方々のコラム記事などをご紹介してまいります。
業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。
業界の動向や時事問題などをテーマにした独自の視点・見解の内容となっておりますので、新たな発見の一助になれば幸いです。
田原中男氏の尖った提案
*毎週の連載から不定期での連載に変更となりました。
2026/2/9 その454 漂流する日本はどこへ行くのか
(今回の記事は選挙結果が出る前でのコメントとなっております)
今回の選挙の結果大きな流れができてしまったようですが、その行先には非常に不安を感じます。
アナロジーで言えば、濱口雄幸首相の暗殺から陸軍若手将校の跋扈が5・15事件2・26事件へと進み大正デモクラシーから正反対の全体主義へと突き進んだ時代がありました。
時代背景として世界大恐慌による大不況、農村部の疲弊、世界的な植民地政策によるブロック経済化などによって日本でも農村部の疲弊があり、主としてその地域の出身者で構成された軍部(特に陸軍)内部で政権への批判が大きくなり「改革運動」としての強力な指導体制への模索と対外拡張主義がありました。
現代に置き換えてみると安倍元首相の暗殺、労働力の2層化により経済的に恵まれない層の出現、それら階層での外国人労働者との競合、人口減少による将来への不安感、世界経済の中での日本の地位低下と中国の台頭などが重なり「何らかの改革運動」が無意識に嘱望されている状況はまさに生き写しです。
それではこれからも同じような経過を辿るのでしょうか、それとも歴史に学びより良い解決法を見つけ出すのでしょうか。
残念ながら選挙結果を見ると昔をなぞっているようです。
そもそも同調圧力の強い日本で小選挙区制を導入した結果、議論が深まるよりもますます現状固定型の政治になってしまったのではないのでしょうか。
小選挙区制の基本は候補者の議論、多くの場合2大政党ないし多くても3党程度での選挙を想定した制度で十分な時間と機会があることが前提ですが日本では国政選挙でも選挙期間はせいぜい2週間程度、これでは討論会はできませんので「名前の連呼」という日本独特の選挙活動になってしまいます。
却って中選挙区時代の方が同じ政党内でも競争があり議論があったので選挙のやり方にまで立ち戻って本当に何がより良いのかという議論から始めるべきでしょう。
チャーチル元首相の言葉として「選挙とはより悪くない候補者を選ぶもの」という言葉がありますが同じようにアメリカ大統領選挙でもニューヨークタイムズ紙が「より悪くない候補者に投票を」と呼びかけたことがあります。
選挙は常により良い候補者の争いになるとは限らず、どちらも嫌だという可能性も多々あるのですがその場合の判断基準を示しています。
残念ながら日本では多くの場合「より悪くない方を」というよりは「よくわからない場合は前と同じ」という判断が強いようでこれが選挙を何回やっても体制に変化がない原因でよほどの「風」が吹かない限り現状維持となり、候補者もそれに慣れてしまって積極的な提案、改革、議論が薄く「情」に訴えるようなことになってしまっています。
同調圧力をうまく使い、結果的に皆が望む方向と異なる方向へと世の中が変わっていってしまう危惧は拭えません。
予測が当たらないことを願うばかりです。
2026/2/9 その454 漂流する日本はどこへ行くのか
(今回の記事は選挙結果が出る前でのコメントとなっております)
今回の選挙の結果大きな流れができてしまったようですが、その行先には非常に不安を感じます。
アナロジーで言えば、濱口雄幸首相の暗殺から陸軍若手将校の跋扈が5・15事件2・26事件へと進み大正デモクラシーから正反対の全体主義へと突き進んだ時代がありました。
時代背景として世界大恐慌による大不況、農村部の疲弊、世界的な植民地政策によるブロック経済化などによって日本でも農村部の疲弊があり、主としてその地域の出身者で構成された軍部(特に陸軍)内部で政権への批判が大きくなり「改革運動」としての強力な指導体制への模索と対外拡張主義がありました。
現代に置き換えてみると安倍元首相の暗殺、労働力の2層化により経済的に恵まれない層の出現、それら階層での外国人労働者との競合、人口減少による将来への不安感、世界経済の中での日本の地位低下と中国の台頭などが重なり「何らかの改革運動」が無意識に嘱望されている状況はまさに生き写しです。
それではこれからも同じような経過を辿るのでしょうか、それとも歴史に学びより良い解決法を見つけ出すのでしょうか。
残念ながら選挙結果を見ると昔をなぞっているようです。
そもそも同調圧力の強い日本で小選挙区制を導入した結果、議論が深まるよりもますます現状固定型の政治になってしまったのではないのでしょうか。
小選挙区制の基本は候補者の議論、多くの場合2大政党ないし多くても3党程度での選挙を想定した制度で十分な時間と機会があることが前提ですが日本では国政選挙でも選挙期間はせいぜい2週間程度、これでは討論会はできませんので「名前の連呼」という日本独特の選挙活動になってしまいます。
却って中選挙区時代の方が同じ政党内でも競争があり議論があったので選挙のやり方にまで立ち戻って本当に何がより良いのかという議論から始めるべきでしょう。
チャーチル元首相の言葉として「選挙とはより悪くない候補者を選ぶもの」という言葉がありますが同じようにアメリカ大統領選挙でもニューヨークタイムズ紙が「より悪くない候補者に投票を」と呼びかけたことがあります。
選挙は常により良い候補者の争いになるとは限らず、どちらも嫌だという可能性も多々あるのですがその場合の判断基準を示しています。
残念ながら日本では多くの場合「より悪くない方を」というよりは「よくわからない場合は前と同じ」という判断が強いようでこれが選挙を何回やっても体制に変化がない原因でよほどの「風」が吹かない限り現状維持となり、候補者もそれに慣れてしまって積極的な提案、改革、議論が薄く「情」に訴えるようなことになってしまっています。
同調圧力をうまく使い、結果的に皆が望む方向と異なる方向へと世の中が変わっていってしまう危惧は拭えません。
予測が当たらないことを願うばかりです。
コラム著者 BMDリサーチ代表 田原中男氏
1946年生まれ。東京大学経済学部、ハーバードビジネススクール(PMD)CIA(公認内部監査人)
1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ(http://www.bmd-r.com)代表
1970年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築。2003年からはグローバルなソニーグループ全体の内部統制体制構築に勤める。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、現在、内部統制コンサルティングBMDリサーチ(http://www.bmd-r.com)代表
田原中男氏の尖った提案 バックナンバー
バックナンバーは下記URLよりご覧下さい。
BMDリサーチ http://www.bmd-r.com
BMDリサーチ http://www.bmd-r.com